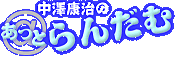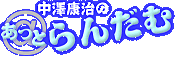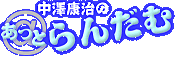インターネットでORP(酸化還元電位)について検索してみました。
温泉水でも注目されてきているようです。測定器は10万円以下で簡単に計れ、数値がはっきりして分かりやすいのですが、意外に難しい概念のようです。
素人考えですと、老化などの諸病の根源が「活性酸素」にあるならば「活性水素」があって両者が出会えば無害な水が出来るので万事OKになります。
日本温泉総合研究所によりますと酸化還元電位(ORP)は、水素イオン濃度や温度との関係が深いこと、また気体水素は安定していて「活性水素」は電気分解の陰極でしか発生しそうもないとの事。酸化還元電位(ORP)がいくら低くても活性水素がなければ意味が薄いということでした。
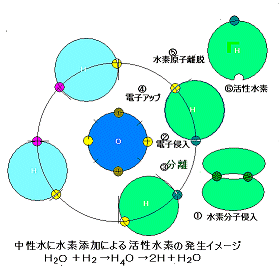
電気分解ではなく、ただ水素を吹き込んだ水でも、溶存酸素が低くて、溶存水素が高く、そして酸化還元電位は低くなるようです。そもそも「活性水素」の存在は九州大学の白畑教授が元祖ですが未だ学会では認められていないようです。同研究所ではどちらかと言えば認めているようですが慎重でした。
しかし酸化還元電位は、活性水素問題とは別に、対象物が酸化されやすいか(電子を取られやすいか)還元されやすいか(電子を受けやすいか)の目安になりそうです。そこで、微生物や我々の身体は、電子を取られると酸化破壊され、与えられると還元保護されるようです。もっとも我々の身体は破壊されるのを前提に抗酸化物質を作り、または逆用して身体を守っていますので、過保護にすると却って自然治癒能力を低下させるかもしれません。そこで紫外線や酸化浴等の外部からの刺激に敏感な方や、機能が衰えた人、アトピーなどの方に還元系の保護が必要になると考えられます。
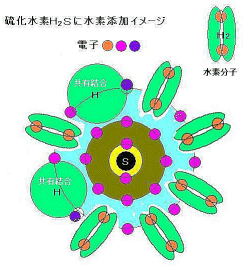
さてブルーマーキュリー社の電解によらない中性の還元水について考えてみました。密閉されたタンクの中の水に水素を吹き込むとまず水中に溶けている酸素と結合して水になって酸素を減らし、代わりに水素分子が水の中に入りそうです。次に考えられるのは、水分子H2Oの中の水素と共有結合をしていない電子の中に入りそうです。気体の水素H2が共有結合のまま入り込むと、L殻の電子2個がK殻に上がり、2つの水素はL殻で酸素と共有結合してH4Oになる事が(図参照)考えられます。この水が一気圧の現状態に戻るとき、不安定なK殻の電子がL殻に戻り共有結合の水素原子が離れ、一時的に単体(活性水素様)となるのではないでしょうか。酸化還元電位はマイナス400mvくらいに下がり、表面張力が強く盛り上がり、油のようなトロリとした感じです。
入浴すると何時までもぽかぽか保温力があるのは粒子が細かく毛穴を塞ぐためでしょうか。ぐったりするのは溶存酸素が少ないためで、保水力があるのは空気中の酸素と結合して水ができるためでしょう。水と硫化水素はH2OとH2Sで、よく似ています。同じ事が硫化水素でも起こっている可能性があります。草津温泉の「わたの湯」や「白旗源泉」がマイナス90mvなのは、密封された地下空間で硫黄に水素が添加されたからでしょう。酸化還元電位(ORP)は、源泉からの距離が近くて、密閉型された引湯の方が低く、遠くて開放されているほうが上がるのも頷けます。